旤偺榚栶 堦屲
惔椓揳 孂宍偺憢 丂娙慺側幚梡偺憿宍 丂 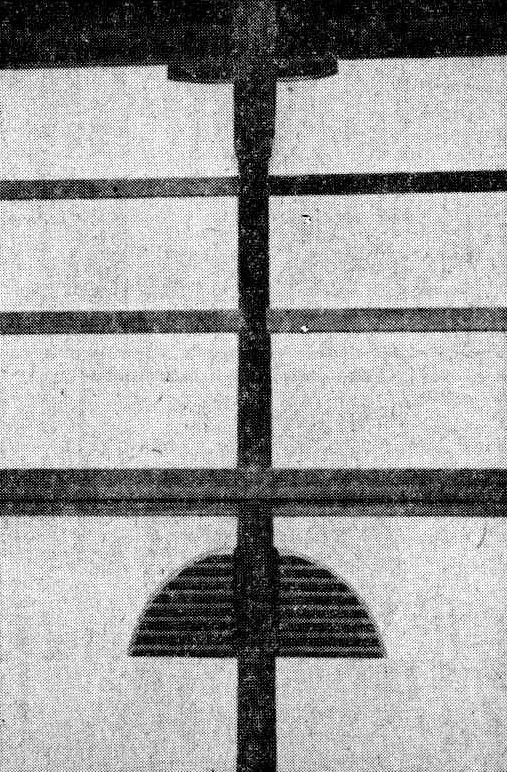
旤偺榚栶 堦屲
惔椓揳 孂宍偺憢 丂娙慺側幚梡偺憿宍 丂 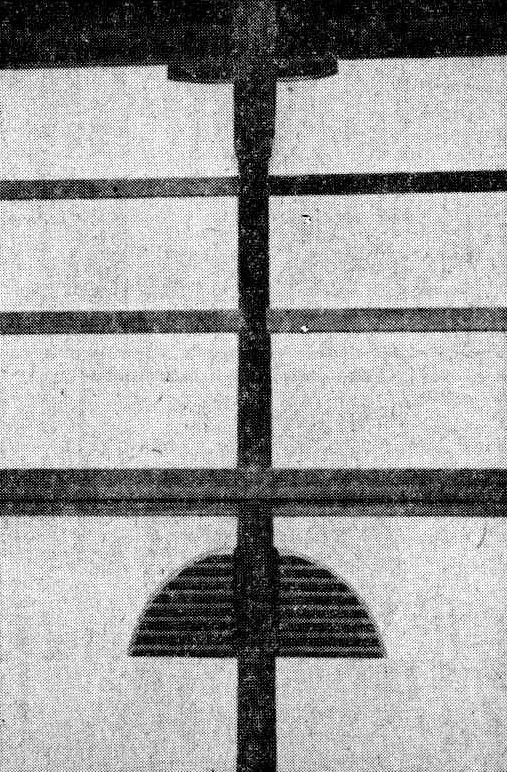
丂暯埨嫗偵偍偗傞揤峜偺廧嫃偨傞峜嫃偼撪棤(偩偄傝)偲偄傢傟偨偑丄壩嵭丄暫棎側偳偺偝偄偵偼椪帪偵巗奨抧偺岞嫧(偔偘)傗戝恇側偳偺揁戭偵堏傝壖偺峜嫃偲偝傟傞偙偲偑懡偐偭偨丅偄傢偔搚屼栧揳丄娬堾揳丄媨彫楬揳丄嶰忦揳摍乆悢懡偄偑丄幚偼尰嵼偺嫗搒屼強偼偦偺棦撪棤(偝偲偩偄傝)偺堦偮偱偁傞搶摯堾搚屼栧揳(傂偑偟偺偲偆偄傫偮偪傒偐偳偱傫)偺敪払偟偨傕偺偱偁偭偰丄撿杒挬偺偼偠傔偛傠栺榋昐嶰廫擭慜偵偙偺応強偵掕傑偭偨傕偺偱偁傞丅
丂偟偐偟偙偙偑惓摑側峜嫃偲側偭偨偺偼撿杒挬摑堦偺戞昐戙屻彫徏揤峜埲屻偱偁傞偲偄偊傞丅偦偺屻偄偔偳偲側偔從偗偰偼嵞寶偝傟偰偒偨偑丄偦偺偮偳偺廋曗丄夵廋偵偲偳傑傝丄偦傟偼暯埨挬戝撪棥偺拞偺峜嫃偲庯偺曄傢偭偨宍偱峕屗帪戙偵媦傫偩丅岝奿揤峜偺屼戙偵側傝屆揟尋媶偺棽惙偵敽偄丄姲惌擭娫偵棤徏屌慣偺晄媭偺柤挊乽戝撪棤恾峫徹乿傪嶲峫偲偟徏暯掕怣偺憤巜婗偺傕偲偵丄屆惂偵拤幚偵暯埨挬偺撪棤偺巔傪暅尦偟偨偺偑偨偩偄傑偺屼強偱偁傞丅傕偭偲傕偦偺屻埨惌擭娫偵墛忋偟姲惌搙偺婯柾偵傛偭偰偝傜偵嵞寶偝傟偨丅
丂偙偺嫗搒屼強偺側偐偺丄暯埨挬偵偍偗傞揤峜偺擔忢偺廧嫃偱偁偭偨惔椓揳偺曣壆(偍傕傗)偺惣撿
嬿偲婼偺娫偺搶撿嬿偲揳忋(偱傫偠傚偆)偺娫偺杒懁惣嬿嫬偺敀暻偵偮偔傜傟偨敿寧宍偺崅憢偑孂宍(偔偟偑偨)偺憢偱偁傞丅憢偲偄偊偽傊傗偲奜晹偲偺棳捠岥偱偁傞傢偗偩偑丄孂宍偺憢偼曣壆(揤峜偺屼嵗強)傗婼偺娫(彈姱偺媗傔強)偐傜丄揳忋偺娫偡側傢偪懁嬤偺帠柋傪偲傞傊傗傪偺偧偒傒傞偙偲偑偱偒傞傛偆偵嶌傜傟偨摿庩側崅憢偱偁傞丅
丂搆慠憪戞嶰廫嶰抜乽崱偺撪棤嶌傝弌偝傟偰桳怑(備偆偦偔)偺恖乆偵尒偣傜傟偗傞偵偄偢偔傕擄側偟偲偰偡偱偵慗岾偺擔偪偐偔側傝偗傞偵尯婸栧堾屼棗(傠偆)偠偰
噣娬堾揳偺偔偟偑偨偺寠偼傑傠偔丄傆偪傕側偔偰偧偁傝偟噥偲嬄偣傜傟傞乿偆傫偸傫偲偁傝丄孂宍偺憢偺偙偲偼屆偔偐傜榖戣偵側偭偰偄偨傛偆偱偁傞丅
偙傟偼栺榋昐巐廫屲擭慜偵偱偒偨晉彫楬撪棤亖擇忦晉彫楬亖偑棊惉偟偰偍偐偊傝傕嬤偔側偭偨偁傞擔丄桳怑屘幚偵捠偠傜傟偨屻怺憪揤峜偺斳(偒偝偒)尯婸栧堾偑屼棗偵側偭偰丄
桳柤側娬堾撪棤亖擇忦惣摯堾亖偺孂宍偺憢偺偙偲傪傛偔抦偭偰偍傜傟偰娵偄傆偪側偟偺傕偺偵嶌傝偐偊傜傟偨偙偲傪偟傞偟偨傕偺偱偁傞丅娙慺側側偐偵傕幚梡偵揔偟偨崅憢偱偼偁傞丅
(堦嬨榋堦擭丠寧丠擔丂怴暦偺愗敳偒婰帠傛傝)
丂
丂乮愇愳拤丒媨撪挕嫗搒帠柋強挿乯